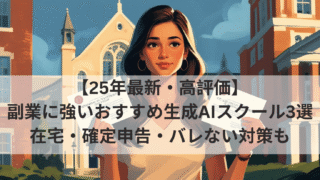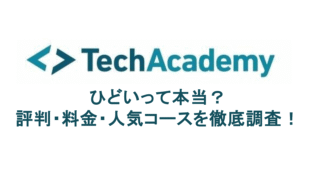更新日:2025年8月2日
公開日:2025年8月2日
※最新情報は公式ページをご確認ください。
※本記事には広告が表示されます
「年収を上げたいなら、転職しかない」そのように感じている方は少なくないと思います。私自身、そう考えていた時期がありました。しかし今は収入を上げる手段として副業を強くおすすめします。
なかでも生成AIを使った副業は時間やスキルに制約があっても小さく始められ、収入を増やすための“現実的な選択肢”としてとても人気が高まっています。
とはいえ、いきなり月に何十万円もの金額を稼ぐ必要はありません。初めは月3〜5万円の収益でも、年間で見れば50万円ほどのプラスになります。転職で昇給するのと同じインパクトを副業で十分に実現できるのです。
さらに、副業は「本業+αの収入源」になるだけでなく、将来的に転職や独立、起業といった次のキャリア選択にもなり得ます。また、これが一番のメリットだと思いますが、私の経験上副業で得たスキルや知見が本業に良い効果を与える可能性がとても高いのです。
この記事では、生成AIを活用しながら、無理なく年収+100万円を目指すための戦略を紹介します。
具体的には、
- 年間+100万円の現実的な道筋(数字で分解)
- 収益を生みやすいAI副業の選び方
- 継続するための習慣とステップ
- 税金や副業ルールの注意点
- 独学とスクール、どちらが向いているか
といったポイントを、私自身の経験も交えながら、丁寧にお伝えしていきます。
まずは「転職しなくても収入は増やせるかもしれない」という視点を得ていただければ幸いです。
「年収+100万円」は副業で実現できるのか?
副業で「年収+100万円」を実現することは、本当に可能なのでしょうか?
結論から申し上げると、それは十分に可能です。
収入と手取りを分解する:月いくら稼げばいい?
まずは、「年収+100万円」をシンプルに月収ベースで考えてみます。
100万円 ÷ 12ヶ月 = 約8.3万円。
つまり、月8〜9万円の副収入があれば、年間100万円の上積みが達成できます。
ここで注意したいのは、「すべてが手取りになるわけではない」という点です。
副業収入には税金(所得税・住民税)がかかりますし、収入の種類によっては経費の計上が必要な場合もあります。
例えば、月10万円稼いで経費が2万円かかり、税金が1.5万円引かれたとすれば、手取りは約6.5万円。この場合でも、年間では約78万円が手元に残ります。
このように、“手取りで年+100万円”を目指すなら、月12〜13万円前後が1つの目安になります。反対に、税引き前で年+100万円(=月8〜9万円)でも、十分大きな意味があると私は思っています。
「時間・スキル・税金」から逆算する副業設計
では、その月8〜10万円をどのように捻出するか。
これは「何を副業にするか」よりも先に、「自分にとって無理のない設計を描けるか」が大切だと感じています。
たとえば、以下のような3要素を意識して逆算してみるのが有効です。
- 時間:週にどのくらいの作業時間がとれるか?(例:平日30分+週末2時間)
- スキル:今の自分に何ができるか?新たに学ぶ余地は?
- 税金・制度:副業が会社にバレない仕組み、確定申告の有無などを把握しておく
これらを踏まえて、「月3万円×3種類」や「月8万円×1ジャンル」のように、無理なく、でも狙いを持った副業を設計することがポイントになります。
私自身、「時間がある日だけやる」スタイルで始めた副業が、気づけば毎月数万円の安定収入になっていたことがあります。
最初から完璧に設計する必要はありませんが、“何をゴールとするか”を決めておくことで、迷わずに済みました。
転職に比べて副業が“柔軟に挑戦しやすい”理由
転職ももちろん、年収を上げる有効な手段です。
ただし、転職には「募集要件とのマッチ」「タイミング」「面接対策」など、越えるべきハードルが多くあります。
一方、副業はもっと柔軟です。
- 時間を限定できる
- 小さく始められる
- 仮に合わなければやめてもいい
この“リスクの低さ”が、副業の最大のメリットだと私は考えています。
特に、生成AIを使った副業は初期投資が少なく、成果物をテンプレート化・自動化しやすいため、「週2〜3時間の積み重ね」が収入につながる構造をつくりやすいのです。
副業で月数万円の収入を得られると、「お金を稼ぐこと=雇われること」という感覚が少しずつ変わっていきます。
この視点の変化が、将来的に転職や独立といった次のステップへの自信にもつながっていくのです。
副業で安定収入を得るための「3ステップ戦略」
副業で継続的に収入を得るには、いきなり高収益を目指すのではなく、「小さく始めて、仕組みにしていく」という視点が欠かせません。
私自身も経験しましたが、最初から完璧なビジネスモデルを組もうとすると、動き出す前に挫折してしまいます。
ここでは、生成AIをうまく活用しながら、安定した副収入を目指すための3ステップを紹介します。
STEP1:収益に直結しやすい“AI活用型ジャンル”を選ぶ
副業と一口に言っても、選べるジャンルはさまざまです。
その中で、生成AIを活用しやすく、かつ収益化のスピードが比較的早いジャンルを選ぶことが、成功への第一歩です。
たとえば、以下のような分野は、個人でも始めやすく、成果が見えやすい傾向があります。
- ChatGPTを活用した記事・キャッチコピー制作
- MidjourneyやCanvaでのSNSデザイン・バナー制作
- NotionやGoogleスライドでの提案資料作成代行
- WhisperやOtterでの音声文字起こし
- Zapierなどを使った業務フロー自動化・改善提案
私が特に推したいのは、「すでに本業で関わっている作業を、AIの力で効率化できるもの」を選ぶこと。
ゼロから学ぶよりも、今あるスキルにAIを“掛け算”する方が、収益化までの距離が圧倒的に短くなります。
STEP2:テンプレ・プロンプトを使って“時短と品質”を両立させる
生成AIの強みは、“型”さえ整っていれば、再現性のあるアウトプットを高速で作れる点にあります。
副業として継続するには、単発の成功ではなく、「短時間でも安定して納品できる仕組み」が重要です。
私も、ChatGPTで記事を作成するときには、以下のような手順を型にしています。
- 顧客の業種・目的に合わせたプロンプトテンプレートを用意
- 構成・見出し・語調を明示的に指示する
- 必要に応じてWordやGoogle Docsに整形して納品
テンプレートとプロンプトを整備することで、「ゼロから考える工数」を最小限に抑えられます。
副業を始めたばかりの頃ほど、こうした“作業の型化”が精神的な負担を減らしてくれます。
STEP3:成果物を小さく試しながら“実績化→収益化”へつなげる
副業を軌道に乗せるためには、「まず世の中に出してみる」ことが何より大切だと実感しています。
どれだけ良い成果物が作れても、自分の中だけで完結していては何も始まりません。
最初のアクションとしておすすめなのは、以下のようなアウトプットの“軽量リリース”です。
- クラウドソーシングでの小規模案件への応募
- 自分の制作物をX(旧Twitter)やnoteで発信
- 無償提供→フィードバック獲得→改善→有償化
「実績ゼロでは受注できない」と思いがちですが、生成AIを使えば短時間で複数パターンの提案を作ることも可能です。
評価よりもまず“場数”を意識することで、経験値と信用が少しずつ積み上がっていきます。
副業で安定収入を得るには、「自分の型を磨く」→「試す」→「再利用する」、このサイクルを回すことが不可欠です。
生成AIは、まさにこの仕組み化に最適な相棒だと私は感じています。
AI副業の種類と特性:自分に合うジャンルをどう選ぶか?
副業を始めようと思っても、「どのジャンルが自分に向いているのか分からない」という悩みは尽きません。特に生成AIのような新しい技術を扱う場合、ツールも手法も日々進化しているため、迷って当然です。
私自身、最初は「どれも面白そうだけど、どれが稼げるのか分からない」と感じていました。けれど今では、“収益性×再現性×継続性”という3つの軸で判断することで、自分に最適な副業ジャンルを見極めやすくなったと感じています。
この章では、代表的なジャンルの特性、費用対効果の目安、そして判断に役立つ「診断軸」を整理してお伝えします。
代表的な5ジャンルの特徴と特性(執筆/デザイン/資料作成/自動化/生成アプリ)
1. ライティング・執筆系(ChatGPT)
ChatGPTなどを活用して、ブログ記事・LP・キャッチコピー・商品紹介文などを制作。
文字単価は1〜2円が主流で、1時間に1,000〜1,500文字程度を書ける方なら、時給1,000〜3,000円は狙えます。
※出典:クラウドワークス報酬目安
- 得意分野:言語化が得意、読書好き、構成力に自信がある人
- AI活用:SEO構成案・仮見出しの提案、文体変換などにChatGPTが有効
2. デザイン制作系(Midjourney/Canva)
SNS用の投稿画像やバナー制作で人気。Midjourney(月10ドル〜)やCanva(無料プランあり)など、初期投資は月1,500円前後から始められます。
1枚あたり3,000〜10,000円の案件もあり、時給換算では3,000円超も現実的です。
- 得意分野:見た目・バランス感覚に敏感な人、SNS投稿を見るのが好きな人
- AI活用:プロンプト+構図指定で複数パターンを高速生成 → 商用素材に編集
3. 資料作成・構成支援(Notion/Googleスライド)
ChatGPT×Notionを使えば、構成から要点整理・清書までワンストップで対応可能。営業職・企画職出身者は特に有利です。1件5,000〜15,000円の実績も多く、論理構成力がそのまま価値になります。
- 得意分野:論理的思考力、提案力、本業での資料作成経験がある人
- AI活用:ヒアリング内容から要約文案、構成図解まで自動化しやすい
4. 業務自動化支援(Zapier/Make)
ZapierやMakeなどを使ったSaaS連携・定型業務自動化ニーズが急増中。
月額3,000円前後のツール投資で、1案件あたり3,000〜10,000円の報酬も。中小企業の“ノーコード担当”として継続案件化する例もあります。
- 得意分野:効率化思考、SaaSツールに慣れている人、ノーコード経験者
- AI活用:自動化したログをChatGPTで要約し、報告レポート化まで自動
5. 生成AIアプリ・プロンプト商品化(GPTs/Replit)
GPTsを使ったチャットボットの設計や、Replitでの簡易Webアプリ作成で副業化する人も登場しています。
ただし、App Store手数料(20〜30%)や集客負荷があるため、成果報酬型かつ粗利管理が必要です。
- 得意分野:構築好き、学習意欲が高い人、SNS・集客も苦にしない人
- AI活用:ユーザー課題を想定したプロンプト設計で“再利用価値”を高める
難易度・時給・初期投資・向いている人【まとめ比較】
| ジャンル | 難易度★ | 時給目安 | 初期コスト | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| ライティング | ★★☆☆☆ | 1,000〜3,000円 | PC+ChatGPT(無料〜) | 言語センス/構成が得意 |
| デザイン | ★★☆☆☆ | 2,500〜4,500円 | Midjourney+Canva(月1,500円) | 視覚重視タイプ/インスタ慣れ |
| 資料作成 | ★★★☆☆ | 2,000〜5,000円 | Notion/Google(無料) | ロジカル思考/本業で作成経験あり |
| 自動化支援 | ★★★★☆ | 3,000〜10,000円 | Zapier:約3,200円/月 | 効率化好き/ノーコード経験者 |
| アプリ開発 | ★★★★★ | 不定(成果型) | GPTs等:無料〜 | 構築好き/SNS発信もいとわない |
※難易度は「習得時間」「設定負荷」「案件獲得難易度」を合算した筆者評価です。
副業選びを誤らないための「3つの診断軸」
- 再現性があるか? → テンプレ化・ルーティン化して継続しやすいか
- 時給効率が見合うか? → 限られた時間で収益を出せるか
- 興味があるか? → 面白さ・楽しさがあるか(=継続の源)
✅ 法務・リスクチェック:副業初心者が気をつけたい4点
- 著作権・商標:商用利用の可否を必ず確認
- 景表法:「月収100万」など根拠のない表現は控える
- 副業規定:就業規則を確認し、住民税は普通徴収を検討
- 税務処理:雑所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要
稼ぐ前に知っておくべき税金と副業ルール
「副業で稼げたけど、あとから税金や会社バレで後悔した」
そんな声は、思っている以上に多く耳にします。特に生成AI副業はスタートが手軽な分、法務や税務への意識が後回しになりがちです。
私自身、最初は「副業=おこづかい」くらいの感覚でしたが、年収+100万円を超える規模になると、きちんと仕組みを知っておくことの大切さを実感しました。
この章では、副業を始める前に押さえておきたい「税金」「副業ルール」「著作権やAI生成物の扱い」について、できるだけ分かりやすくお伝えします。
年収+100万円で発生する税務処理とは?
副業収入が年間100万円程度になると、必ず意識すべきなのが「税務処理」です。
会社員の方で、本業とは別に年間20万円を超える副業収入があった場合、原則として確定申告が必要になります(※雑所得扱い)。
ポイントは、「20万円以下なら申告しなくてもいい」というわけではないこと。
実際には、住民税の申告が必要だったり、経費や帳簿をつけていなかったことで後々困るケースもあります。
とくに注意したいのは次の2点:
- 副業が「事業所得」とみなされるか「雑所得」か(収益規模と継続性による)
- 経費を引くためには、領収書・帳簿などの証拠を保管する必要がある
副業収入が安定し始めたら、早めに「会計アプリ(例:freee、マネーフォワード)」を使って管理を始めるのがおすすめです。
最初は手間でも、後で「あの時からやっておいてよかった」と感じるはずです。
住民税“普通徴収”と確定申告の注意点
「副業がバレたらどうしよう」と心配な方にとって、最も大事なのが「住民税の納付方法」です。
なぜなら、副業の住民税が本業の給与から天引き(特別徴収)されると、会社側に副業収入の存在が知られる可能性があるからです。
そこで重要なのが「普通徴収」という選択肢です。
確定申告時に「住民税は自分で納付する(普通徴収)」と明記すれば、副業分はあなた自身が直接支払う形式になります。
これによって、会社に通知されるリスクを最小限にできます。
ただし、自治体によって対応が異なる場合もあるため、住民票のある市区町村の税務課に事前確認することをおすすめします。
また、雑所得でも「副業で帳簿をつけているか」「継続的な活動か」などにより、税務署の判断で事業所得になることもあります。
収益規模が年100万円を超えそうな場合は、青色申告の検討も視野に入れておくとよいでしょう。
副業禁止規定・著作権・AI生成物の扱いにも注意
税金だけでなく、会社員としての立場を守るためにも、「副業に関する就業規則」を必ず確認しておきましょう。
多くの企業では、「競業に当たらない限りOK」「申請すれば可能」といった運用になってきていますが、
中には「事前申請必須」「一切禁止」としているケースもあります。
また、生成AIを活用する副業には、特有の法務リスクも存在します。たとえば:
- 著作権侵害
AIに学習させた素材が既存作品に類似していた場合、著作権者から指摘を受ける可能性があります。 - 商用利用NGのツール
Canva無料プランなど、一部機能は非商用利用限定です。規約は必ず確認しましょう。 - 生成物の著作権帰属
ChatGPTの出力は「著作権なし」が基本ですが、クライアントとの契約次第では納品後に帰属が移転する場合もあります。
そしてもうひとつ、見落としがちなリスクが「景表法(誇大広告)」です。
「誰でも月100万円稼げる」といった表現は、根拠のない限り避けるべきです。
この章をまとめると、副業で稼ぐ上で「リスクの正体を知っておくこと」は、とても大事な準備です。
不安を感じたら、税理士や労務の専門家に相談するのも一つの選択肢ですし、最近では副業サポートを行うオンラインスクールなども増えています。
稼ぎ始めてから焦るよりも、「始める前に最低限のルールを知っておく」——これが、副業を長く続けるための第一歩だと私は感じています。
副業で成果が出る人の共通点と“落とし穴”パターン
副業に取り組む人は年々増えていますが、「思ったより稼げなかった」「3ヶ月でやめてしまった」という声も後を絶ちません。
一方で、限られた時間でも着実に成果を出している人たちがいるのも事実です。
何がこの差を生むのか? 私自身や周囲の事例をもとに見えてきたのは、“才能”よりも“やり方”の違いでした。
この章では、「やりきる人」の習慣や考え方、そして「うまくいかない人」が陥りやすいパターンを整理してお伝えします。
やりきる人は何をしているか?(習慣設計・目標の粒度)
副業で成果を出す人には、いくつかの共通した習慣があります。特別なスキルや時間があるわけではなく、行動を“仕組み化”しているかどうかが鍵です。
たとえば、以下のような工夫が目立ちます:
- 行動目標を小さく設定している
例:「今週は“提案用ポートフォリオを1つ出す”だけ」など、“完了条件”を具体化して迷わない - スケジュールに“予約”する習慣がある
副業の時間を「空いた時間にやる」ではなく、「火・木は20〜21時」と事前にブロックしている - SlackやNotionを使って自分の進捗を“見える化”
進捗を記録したり、タスクを整理するだけでも継続率が大きく変わります
また、もうひとつのポイントは“比較する相手”です。
成功者の月収を見て落ち込むよりも、「昨日の自分と比べて進んだか?」にフォーカスする人の方が、結果的に続いています。
うまくいかない人の特徴と共通リスク
一方で、副業でつまずきやすい人には、共通する“落とし穴”があります。よくあるパターンを以下にまとめます:
- ジャンルやツールを頻繁に変える
「Webライターは稼げないかも→画像生成の方が良さそう→やっぱり自動化…」と移り気になると、どれも中途半端に終わってしまいます。 - 成果=報酬と捉えてしまう
はじめの数件は“信用”を積むフェーズです。単価より「納品経験」「フィードバック」の価値を意識できないと、続けにくくなります。 - すべて独学で完結させようとする
無料リソースで学べる範囲には限界があります。途中で「何が正解か分からない」と迷いやすい人ほど、環境やサポートを活用すべきです。
これらに共通するのは、「完璧を目指すあまり動けなくなる」傾向です。
副業は“始めたもの勝ち”であり、“完璧より継続”という視点が重要です。
副業SNS・煽り情報に踊らされない思考術
副業界隈のSNSでは、「月100万円達成」「一晩で5万稼げた」といった成功体験があふれています。
もちろん中には事実もありますが、多くは一部の実績や広告目的の切り取りです。
私が意識しているのは、以下のような“思考フィルター”です:
- 「再現性」を軸に情報を見る
「この人だからできた」のではなく、「自分でも同じ条件でできるか?」で判断する - 「誰に向けた情報か」を見極める
“煽る系”はフォロワー獲得が目的のことが多く、本質的なノウハウは表に出ていない - 「すぐ稼げる」情報より、「続けられる」設計に目を向ける
急激な成果より、安定的な収入をつくる方が長期的に見ると確実です
SNSを完全に遮断する必要はありませんが、あくまで参考情報と割り切ること。
「自分の副業は、自分のペースで育てていく」という感覚が、焦りを和らげてくれます。
副業は、たった一つの正解があるわけではありません。
けれど、「やり方」と「考え方」の軸を整えておくだけで、再現性はグッと上がります。
そして何より大事なのは、「うまくいっている人も、最初は不安だった」ということ。
その不安を“どう乗り越えていったか”にこそ、次の一歩のヒントがあるのだと私は思います。
独学か?スクールか?副業を続ける“学び方”の選択肢
副業を始めるとき、多くの人が悩むのが「どうやって学ぶか?」という問題です。
生成AIの副業は、ツールの操作だけでなく、プロンプトの書き方、ポートフォリオの整え方、さらには案件応募や納品の仕方まで、多岐にわたります。
特に初めて副業に挑戦する方や、忙しい日常の中で“限られた時間で成果を出したい”と考えている方にとっては、「どの学び方が自分に合うのか?」を見極めることが、成功率に直結します。
ここでは、「独学」と「スクール」という2つの主な選択肢を軸に、どんな人にどちらが向いているのか?を具体的にお伝えしていきます。
【あわせて読みたい】【25年最新・高評価】副業に強いおすすめ生成AIスクール3選|在宅・確定申告・バレない対策も
独学のメリット・デメリットを再確認
まず、独学の一番の魅力は、“気軽に始められること”です。YouTubeやブログ、SNSなどに無料で情報があふれており、最低限の知識は手に入ります。
コストもかからず、自分のペースで学習できるので、「とりあえずやってみる」という選択肢としては非常に有効です。
ただし、実際に独学で副業を始めた人の多くがぶつかる壁も存在します。
独学のメリット:
- 無料〜低コストで始められる
- 好きなタイミングで学べる
- 自分の興味に合わせて選べる
独学のデメリット:
- 情報が断片的で、体系的に理解しづらい
- 「何が正解か」が分からず迷いがち
- 試行錯誤の時間が長く、成果までが遠い
- モチベーションの維持が難しい
副業は「収益化」がゴールである以上、単なる“知識のインプット”では不十分です。
「習ったことを実践でどう使うか」「継続して成果を出す仕組みをどう作るか」という部分で、独学には限界を感じるケースも少なくありません。
スクールを使うことで得られる時短と再現性
そこで注目したいのが、生成AI副業に対応した“実践型のスクール”です。
最近は単なる教材提供にとどまらず、以下のような“実務サポート”まで組み込まれているスクールが増えています。
- 副業案件の紹介・マッチングサポート
- 納品物に対するフィードバックや添削
- ポートフォリオ作成・SNS発信の指導
- 進捗管理・相談体制・講師からのフィードバック
さらに、スクールによっては副業から転職・起業に発展することも想定して、キャリアのコーチング支援を提供しているところもあります。
これは特に、40代以降の方にとって大きな意味を持つ選択肢です。
40代からの副業は「再出発」ではなく「積み上げの延長線」
40代、50代というのはキャリアの折り返し地点に差し掛かりながらも、「今さら新しいことを始めていいのだろうか」「遅すぎるのでは?」と躊躇する方も少なくありません。
ですが、実際にはこの年代こそ、過去のビジネス経験や職務スキルを“生成AIと掛け合わせる”ことで、独自の価値を生み出しやすいフェーズでもあります。
スクールを「学びの場」としてではなく、「キャリア戦略を一緒に考えるパートナー」として捉えることで、副業は単なる小遣い稼ぎではなく、次の10年をデザインするための準備期間へと変わります。
- 過去の経験を棚卸しし、強みを見つける
- 副業を通じて試し、小さな成功体験を積む
- スクール講師や受講仲間から刺激を得る
- 必要であれば副業→転職や起業へのシフトも視野に入れる
このように、生成AIスクールを“実務+キャリアのコーチング”として活用することは、40代以降の方にとって非常に再現性の高い投資になり得ます。
個人的には、40代以降の方についてはライフシフトラボというキャリアコーチングサービスを利用することを強くおすすめします。興味のある方は下記より公式サイトをご覧ください。
\ 無料の個別相談も実施しています /
【あわせて読みたい】ライフシフトラボは怪しい?評判・料金は?生成AIの新コース解説付き
自分に合った学習スタイル診断(質問チェックリスト)
最後に、「独学か?スクールか?」を選ぶ際の簡単な自己診断リストをご用意しました。
以下の質問のうち、3つ以上が「はい」の方は、スクールを検討してみてもよいかもしれません。
【チェックリスト】
- ✔ 学習に使える時間が限られている
- ✔ 情報が多すぎて、何から始めればいいか分からない
- ✔ 自分のやり方に確信が持てず、不安が残っている
- ✔ 案件応募や納品が初めてで、自信がない
- ✔ 本業と副業をどうつなげるか、整理できていない
- ✔ 将来的に副業から転職や独立を考えている
一方で、以下に当てはまる方は独学でも進めやすい傾向があります:
- ✔ 情報を集めて自分で組み立てるのが得意
- ✔ すでに生成AIや副業経験が少しある
- ✔ 時間に余裕があり、急いで結果を出す必要がない
学び方に“正解”はありませんが、副業を継続し成果を出していくためには、「自分に合った道筋」を見つけることが何より重要です。
もし過去に独学で挫折した経験があるなら、それは“あなたのやり方が悪かった”のではなく、“続けやすい環境が整っていなかった”というだけかもしれません。
生成AIという新しい武器を手に入れ、これからの働き方や収入のつくり方を見直したい——そう考えているなら、スクールという選択肢は、あなたの可能性を広げるきっかけになるはずです。
【あわせて読みたい】【25年最新・高評価】副業に強いおすすめ生成AIスクール3選|在宅・確定申告・バレない対策も
最後に|本業を生かしつつ副業で収入を増やすという発想
生成AIを使った副業には、まだ未知の部分も多いかもしれません。
「本当に自分にもできるのか」「時間が限られていても続けられるのか」――そんな不安を抱えながら、このページまで読んでくださった方も多いと思います。
しかし、今の時代はちょっとしたスキマ時間でもAIを使って仕事ができる環境が整いつつあります。
副業というと、すぐに大きな収入を目指すようなイメージがあるかもしれませんが、そうではなく、まずは「月に数千円」「週2時間だけでも」といった小さな目標で十分です。
大切なのは、「自分にとって無理のないペースで、着実に前に進んでいくこと」だと思います。
そしてそのためには、最初に少しだけ方向性を定めておくこと、つまり、“収益を見据えた学び方”を意識して始めることが、のちの継続や成果につながります。
私自身まだまだ勉強中の身ですが、これからもお役に立てる情報を発信していければと思います。
【あわせて読みたい記事】【25年最新・高評価】副業に強いおすすめ生成AIスクール3選|在宅・確定申告・バレない対策も