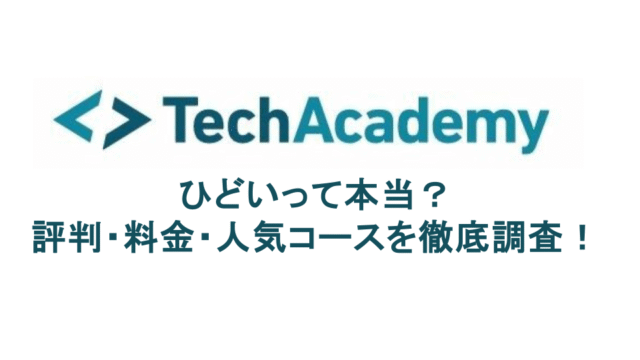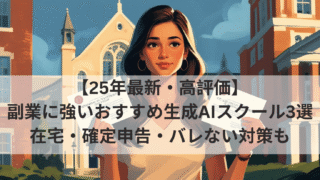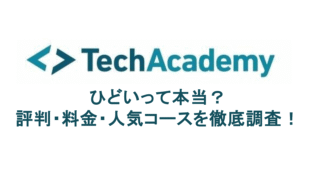更新日:2025年8月8日
公開日:2025年6月23日
※最新情報は公式ページをご確認ください。
※本記事には広告が表示されます
「最先端の業界に挑戦して人生を変えたい。そのためにキカガクでAIを学びたいけど、難しいという評判が気になる。せっかく時間とお金をかけるなら絶対に挫折したくない!」
そのような不安や悩みを抱えているあなたのために、本記事では今話題のAIを学べる人気スクール「キカガク」を徹底調査しました。
まず申し上げると、「難しい」という評判には多くの誤解が含まれています。
確かに、キカガクの「AI・データサイエンス長期コース」では、Pythonや統計、機械学習といった専門的な内容を扱います。そのため、数学などの要素に対して「難しい」と感じる人がいるようです。
ただし、それは内容が難解すぎるというよりも、
- 単に慣れないジャンルであること
- 学生時代の数学に対する苦手意識を引きずっている
- 学習内容が濃いことの裏返し
といったケースがほとんどです。
キカガクでは、Slackでの質問無制限、週1のメンタリング、1500本以上の動画教材など、未経験者でも学び続けられるサポート体制が充実しています。
さらに、もう一つの人気コースである「生成AIビジネス実践コース」については、丁寧に評判を調査すると「難しい」という声すら見かけません。
総務省の情報通信白書によると、日本でいまだに生成AIに触れたことのない方は7割以上にも上るそうです。これは他国と比べて極めて低い数字であり、国家としては由々しき自体ですが、ライバルに差をつけると言う意味では絶好の機会です。
そのような状況で、AIを学んで人生を変えたいとお考えの方は、極めて大きなチャンスを前にしていると言えるでしょう。本記事があなたの学習を支える一助になれば幸いです。
\ 30秒で簡単申し込み /
\ 30秒で簡単申し込み /
難しいという評判は本当?結論:誤解です
「キカガクは難しい」――そう聞いて、不安に感じている方のために、まずはその評判に対する誤解を解いていきましょう。
ここでは、なぜ“難しい”と言われるのか、そしてその実態はどうなのかを、3つの視点から解説していきます。
「難しい」と言われる3つの理由
1. 数学に対して特に学生時代の苦手意識を引きずっている
とくに「AI・データサイエンス長期コース」では、統計学や線形代数、機械学習のアルゴリズムといった、理系科目がしっかりと出てきます。
中学校〜高校レベルの数学知識で理解できる内容がほとんどとはいえ、学生時代に数学に対して苦手意識を抱いていた方は「今だに数学と聞くと身構えてしまう」パターンが多いそうです。
ただし、これはあくまで最初の印象だけであって、分かりやすい教材や充実したサポート体制により基礎から丁寧に学ぶことができるため、問題なくハードルを超えることができます。
2. 環境構築やツール導入時のつまずき
「Pythonの開発環境がうまく動かない」「Jupyter Notebookって何?」こうした環境構築に難しさを感じてしまう方もいます。
しかしキカガクでは、はじめの一歩をスムーズに進めるためのスターターガイドやSlackでのサポート体制が整っており、環境構築もサポート付きで進められます。
また、このような環境構築は他のスクールも同じように必要であるため、それによって「キカガクは難しい」とは言えないでしょう。
3. 実践的で濃い学習内容であり、その分学習期間が長いため
「AI・データサイエンス長期コース」は、AI・機械学習・データ分析・モデル実装・G検定/E資格対策(※併用時)などを一気に学ぶ構成です。
学習動画は約130時間(約1,500本)と明記されており、受講生の平均的な学習時間はおよそ300時間前後と想定されています(※公式FAQ・受講ガイドより)。
そのため、「本気でAIを武器にする」ための実践的な内容が詰まっており、1日1時間前後の学習ペースでもしっかり時間を確保する必要があります。
このボリュームを“忙しい社会人が一人で進める”と考えると、「難しい」「途中で続けられないかも」と感じてしまうのも無理はありません。
ただし、これはある意味健全な悲鳴と言えるでしょう。スパルタを推奨するわけではありませんが、本当に現場で活躍できる人材になるためにはある程度厳しい経験はどうしても必要ではないでしょうか。
また、そもそもAI自体が決して簡単な分野ではありません。しかしだからこそ時間をかけて学ぶ価値があると言えるのではないでしょうか。
難しいという評判の割に“挫折率が低い”理由とは?
とはいえ、実際にキカガクを受講した人たちの声を見てみると、「最初は難しいと感じていたけど、気づいたらしっかり身についた」というパターンがとても多いのです。
なぜかというと、学びを“ひとりにしない”仕組みがあるからです。
- Slackでの質問は回数無制限(平日10:00〜19:00、原則24時間以内に返信)
- 週1回目安のメンタリング(ライブ講義に含まれる。日程・頻度は月によって変動)
- Slackコミュニティで受講生同士が助け合える
- 動画1500本以上で基礎から復習可能
講師陣は「教えるプロ」としての研修を受けたメンバーが揃っており、どんなレベルの質問にもやさしく丁寧に対応してくれます。
“難しい”と感じる瞬間はあっても、ひとりで抱え込まず、「講師に聞く」「仲間に相談する」「少しずつ進める」ことで、しっかりと前進していける環境です。
そして、ある程度難易度の高いカリキュラムをやりきったことが、「あのカリキュラムを修了して卒業できた!」という成長実感にもつながっています。
「生成AIビジネス実践コース」も難しいと言われている?
結論から言えば、「生成AIビジネス実践コース」に対して『難しい』という評判は現時点で確認できませんでした。
恐らく、検索エンジン上では「キカガク 難しい」でまとめて表示されてしまう可能性があるため、長期コースの難易度と混同されるケースが多いのではないでしょうか?
このコースは、主にビジネス職・非エンジニア層を対象としており、プログラミングや数式の知識がなくても始めやすい内容になっています。
内容の中心は以下のとおりです:
- ChatGPTのプロンプト設計・活用法
- 社内データと連携したQ&Aボットの構築
- 社内マニュアルの自動化
- AI導入の社内推進フロー
そのため、初学者でも取り組みやすく、「難しい」と感じる口コミもほとんど確認されていません(Googleレビュー・X投稿調査より)。
今後、生成AIを活用できる人材はあらゆる業界で求められます。
個人的には、どのような立場・職業にあるすべてのビジネスパーソンにおすすめしたいコースです。
\ 30秒で簡単申し込み /
あなたにとっての最適解:2つのコース徹底解説
「AIを学びたいけど、自分に合うのはどっちのコース?」
──そんな疑問を持つあなたのために、キカガクが用意している2つのコースを徹底的に解説します。
1つは、生成AIの活用スキルを短期間で習得し、日常業務の生産性を高めたい方向けの【生成AIビジネス実践コース】。
もう1つは、AIエンジニアやデータサイエンティストを目指す方のために設計された【AI・データサイエンス長期コース】です。
本章では、以下の5つの視点から2つのコースを紹介します。
- ✅ コースの基本情報
- ✅ 受講によって得られる3つの価値
- ✅ このコースが解決できる悩み
- ✅ 特におすすめな人物像
- ✅ 学びとサポートが“キャリアの武器”になる理由
読了後には、あなたの目的にもっとも合った道筋が、きっと見えてくるはずです。
生成AIビジネス実践コース
生成AIは単に指示(プロンプト)を出せばなんでも自動で解決してくれるわけではありません。生成AIから求めるアウトプットを得るためには、相応の技術であるプロンプトエンジニアリングが必要になります。
プロンプトエンジニアリングはまだ日本で馴染みのない技術ですが、すでに海外ではこの技術に習熟したビジネスマンに対して年収4,000万円を支払う企業もあるほどです。
また、生成AIは自分の業務に合わせてカスタマイズすることが可能で、これらの知見も今後ライバルと差をつける大きな要素となるでしょう。
個人的には、立場や業種を問わずすべてのビジネスパーソンにおすすめしたいコースになります。
✅ 基本情報
忙しい社会人でも無理なく取り組めるよう、学習設計はシンプルで現実的です。「仕事と両立できるのか?」という不安にきちんと応えてくれるでしょう。
- 学習内容:生成AIの基礎〜応用、DX企画立案、オリジナルのAIアシスタント作成
- 受講期間:2カ月
- 受講料:264,000円(税込)
- 補助金適用後:最大52,800円(税込)
※専門実践教育訓練給付金の対象となるには所定の条件あり(地域のハローワーク判断により異なります)
✅ 受講で得られる3つの価値
この講座で得られるのは、単なる知識ではありません。日々の業務に“そのまま使える”AIスキルです。
- ChatGPTなど生成AIリテラシー
- 自社の業務に合わせてカスタマイズしたAIアシスタントの導入方法
- ノーコードで扱えるツールを中心とした、非エンジニア向けの実践環境
✅ このコースが解決できる悩み
このコースでは、ライバルと差をつけて時代の先を行くために下記のような悩みを解決することができます。
- AI活用に興味はあるが、具体的な方法が分からない
- ChatGPTは試しているが、日常業務への活かし方に迷っている
- IT部門に頼らず、現場レベルでAIを扱えるようになりたい
✅ 特におすすめな人
このコースは、生成AIを活用して業務を改善したい下記のような方におすすめです
- 業務を改善して自由な時間を増やしたい方
- 現場に新しい視点を加えてライバルと差をつけたい方
- 副業や独立も視野に、これからのキャリアに最適なスキルを身につけたい方
✅ 学びとサポートが“キャリアの後押し”になる理由
自分のペースで学びながらも、困ったときはすぐに相談できる安心感。孤独にならない仕組みが整っています。
- Slackでの質問対応:平日10:00〜19:00(原則24時間以内に順次返信)
- Zoom個別サポートあり(要予約)
- 講義動画:修了後の視聴期限は要問合せ(受講状況により異なる)
業務での実践につなげることを目的とした設計だからこそ、「すぐ使える」「仕事で役立つ」と感じる受講者が多いのも特徴です。
このように、生成AIビジネス実践コースは“キャリアチェンジ”はもちろん“キャリアアップ”に特に適した選択肢です。
「できるだけ現職に近い形でAIを取り入れてみたい」という方は、まずこのコースから検討してみてください。
\ 30秒で簡単申し込み /
AI・データサイエンス長期コース
「AIを“活用する側”ではなく、“作る側”になりたい」
「AIエンジニアとしてキャリアを変えたい」
本コースはそんな思いを持つ方に向けた6カ月の本格講座です。
このコースは、機械学習や深層学習といった専門性の高い知識・スキルを体系的に学び、業界でも通用する“AI人材”を目指す人のために最適です。現場で活きる実装力に直結するカリキュラムが組まれています。
もちろん未経験からのチャレンジでも大丈夫です。
慣れないうちは「難しい」と感じるかもしれませんが、それを乗り越えさせてくれるサポートがとても優れています。
✅ 基本情報
AI人材となるための学習が完全に網羅されています。時間をかけて確実なスキルを身につけたい方には本コースが適していると言えるでしょう。
- 学習内容:Python基礎、機械学習、データ分析、ディープラーニング、企画、要件定義、アプリ開発等
- 受講期間:6カ月
- 費用:792,000円(税込)
- 補助金適用後:最大633,600円(実質負担158,400円)
※専門実践教育訓練給付金の上限:560,000円/受講後1年以内の就業が条件
✅ 受講で得られる3つの価値
AI人材として活躍するための確かなスキルが身につきます。
- 機械学習・ディープラーニング・統計基礎などを網羅するカリキュラム
- E資格に対応(※別途対策コース+事前テスト合格が必要)
- 実務で活かせるポートフォリオ構築支援と開発環境(VS Code/Vertex AI 等)
✅ このコースが解決できる悩み
大手転職サービスdodaと提携した転職サポートが卒業後も利用可能。講師のサポートや仲間の存在が挫折を防ぎます。
- サポートや仲間の存在が独学による挫折を回避
- 卒業後も学びを継続できる環境の確保
- 転職サポートでリスクヘッジも万全
- 補助金で受講料大幅減額
✅ 特におすすめな人
技術を手に入れることで、選べる未来を増やしたい方に。
- 未経験からAIエンジニアやデータサイエンティストを目指したい方
- 数学やプログラミングを基礎から積み上げたい方
- 転職・キャリアチェンジを視野に入れている方
✅ 学びとサポートが“キャリアの武器”になる理由
継続の難しさを理解したうえで、挫折させない仕組みが整っています。
- 約1,500本に及ぶ動画教材(受講後も永年視聴可能)
- 週1回のライブ講義兼メンタリング(スケジュールは月毎に調整あり)
- Slackでの質問サポート:平日10:00〜19:00/原則24時間以内に対応
- 転職支援:dodaとの提携により、IT専門アドバイザーが個別に対応
なお、E資格の受験には別途「E資格対策コース+事前確認テスト満点」が必要なため、受講前に条件を確認しておくと安心です。
\ 30秒で簡単申し込み /
あなたに合った最適なコースはどちら?
2つのコースを比較してきましたが、「結局、どちらを選ぶべき?」と迷っている方も多いはず。
そこでここでは、あなたの現在地や目的別に最適な選択肢を整理してみましょう。
✅ 転職やキャリアチェンジを目指すなら…
→ AI・データサイエンス長期コース
- E資格対策・doda転職支援など「キャリア構築」に直結
- 6カ月間しっかり腰を据えて学ぶことで、AI人材としての自信が得られる
- AIエンジニア/データサイエンティストなど“つくる側”を目指したい人向け
\ 30秒で簡単申し込み /
✅ 今の仕事を変えず、業務効率化・スキル向上をしたいなら…
→ 生成AIビジネス実践コース
- ChatGPTを中心とした生成AI活用を“仕事で使える”形で習得
- 非エンジニア向けなので、技術的ハードルが低い
- 業務改善・副業・デジタルリテラシー強化など、現職への“即効性”を求める人向け
\ 30秒で簡単申し込み /
どちらも教育訓練給付金の対象です(ただし条件あり)
両コースとも「専門実践教育訓練給付金」の対象ですが、受給には下記の注意点があります。
- 給付率:最大80%(上限あり)
- 長期コースの上限:560,000円(→実質負担158,400円)
- 申請タイミングは受講開始1カ月前が目安(要:ハローワークでの事前手続き)
👉 申請条件や必要書類は、お住まいの地域のハローワークで必ず確認しましょう。
迷ったら、まずは無料説明会へ
どちらのコースにもオンラインでの無料個別説明会が用意されています。
無理な勧誘は一切なく、講座の内容やサポート体制、給付金についても丁寧に説明してもらえるため、迷っている方にこそおすすめです。
体験談で「未来の自分」を想像する
未経験から転職に成功した方、社内でのキャリアアップに活かした方──キカガクの受講生たちは、単に知識を得るだけでなく、「人生の転機」を掴んでいます。
ここでは、公式ブログで公開されているインタビューの中から、印象的な事例を3つご紹介。
本章では「AI・データサイエンス長期コース」を受講された方の実体験を取り上げます(※生成AIビジネス実践コースの体験談は2025年8月時点で未掲載)。
あなた自身の未来像と重ねながら、読み進めてみてください。
事例①|「スキルのなさが不安」だった自分が6カ月でAIエンジニアへ
もし、今のあなたが「今の仕事でこのままでいいのかな」「本当は新しいことに挑戦したいけど、スキルがなくて踏み出せない」と感じているなら──土屋さんの話は、きっと参考になるはずです。
土屋さんは、もともと鉄道関連の設備設計に携わる製造業のエンジニアでした。プログラミング経験は大学時代のわずかな経験のみで、AIやPythonには縁がなかったそうです。
それでも、土屋さんの中には「データから価値を見出すような仕事がしたい」という想いがありました。
「機械学習って面白そう。やるなら本格的に学びたい」
そう考えて挑戦したのがキカガクの「AI・データサイエンス長期コース」でした。
単に知識をインプットするのではなく、“実務から逆算されたカリキュラム”に惹かれたと言います。
継続のカギは「一人じゃない環境」と「自走できる力」
もちろん、最初からスムーズにいったわけではありません。長期コースは体系的で実践的です。ときに複雑な課題や難解なエラーにも直面しました。
しかし土屋さんはあきらめませんでした。
その理由として、「仲間の存在」が大きかったそうです。
「みんな同じように悩んでいる。だから、自分だけじゃないと思えた」
Slack上のチームメンバーとの交流は、想像以上に心強かったそうです。
さらに、メンタリングや質問サポートなど、学習のペースを整える仕組みが支えとなりました。
やがて、自走期間には本格的なアプリも開発しました。
WEBカメラの動画を解析し、リアルタイムで物体を検出するAIアプリを作り上げたのです。
「“とにかく調べてやり切る”。そんな力がついたのは大きな自信になりました」
未経験からAIエンジニアへ転職──仕事でAIを使いこなす日々
6カ月の学習を終えた後、土屋さんは転職活動を開始しました。キカガクとdodaが連携する転職支援では、エージェントが講座内容を理解した上で職務経歴書や推薦状を丁寧にサポートしてくれました。
結果、タクシー運行データを扱う企業にAIエンジニアとして転職が決定!
今は、売上予測や需要分析のモデル開発に携わり、近くは「歩行者の行動を予測するAI」など、先進的なプロジェクトにも挑んでいます。
「正直、めちゃくちゃ楽しいです(笑)」
転職前には想像できなかった世界が、今は“日常”になっているのです。
「自分に誇れるスキルがない」と感じているあなたへ
最後に、土屋さんがこんな言葉を残しています。
「今、自分には誇れるスキルがないと感じている人にこそ、このコースをおすすめしたい」
AIや機械学習に興味がある──だけど未経験で不安、数学が苦手、続けられるか心配。
今この瞬間から未来を変えるチャンスはあります。
土屋さんのストーリーから分かるように、皆さん最初は同じだったのです。
※出典:キカガク公式インタビュー
事例②|「40代・未経験でも通用するのか?」営業職からデータサイエンティストへ
「もう年齢的に無理かも」
「文系だし、AIなんて無縁」
そんな思い込みが、キャリアの選択肢を狭めていませんか?
次に紹介するのは、まさにその“常識”を打ち破った受講生のストーリーです。
40代で未経験から「データサイエンティスト」への転職を叶えたkokuboさんの事例を紹介します。
■ エンジニアでも理系大学出身でもなかった
kokuboさんはもともと、自動車部品の製造に関わる技術営業職でした。プラスチック成型に関するプリセールスを担当しながらも、プログラミングとは無縁の日々を過ごしてい多そうです。
工業高校卒のため、高校数学の履修範囲も限定的でした。そのためAI学習の土台となる微分積分や確率統計には不安があったといいます。
■ 受講の決め手は「卒業後も学び続けられる」安心感
複数の講座を比較した中で、kokuboさんがキカガクの「AI・データサイエンス長期コース」を選んだ決め手は、次の点でした。
「卒業後も半永久的に動画が視聴できる。それだけで、“学び続けられる未来”が見えました」
時間的制約や年齢の壁を感じる中でも、自分のペースで学びを継続できる、その安心感が決断の後押しとなったそうです。
■ “手が遅い”という不安も、ゲーム感覚の工夫で乗り切る
自身の理解力や作業スピードに不安があったkokuboさんは、進捗を「クエスト」化して取り組みました。
「進捗率やテストをやり込み要素のように捉えて、楽しみながら学べました」
この工夫が、6カ月間の学習をやり抜く大きな支えとなったそうです。楽しみながら乗り越える姿勢は本当に素晴らしいと思います。
■ チーム学習で「自分の知らない世界」に触れた
学習を支えたもう一つの要素は、チームとの交流でした。他の受講生との学び合いの中で、“新しい知識”や“気づき”に触れることができたといいます。
「E資格保持者の方に勉強法を教えてもらえたのは本当に助かりました」
一人では得られない視点、仲間とだからこそ広がる学習体験が、成長を後押ししているのですね。
■ 身についたスキルと、転職後に感じた“活きる力”
講座修了後、kokuboさんには次のようなスキルが身についていました。
- Pythonによる基礎的なコーディング
- データの前処理と可視化
- 機械学習・ディープラーニングの理論と実装
- 画像分類/自然言語処理 など
受講中から始めた転職活動で、無事にデータサイエンティストとして転職に成功されました。現在はプリセールス業務も兼任しながら、受託案件に従事されています。
特に画像分類のスキルは、実務で大いに活かされているとのこと。
■ kokuboさんから、これからの受講生へメッセージ
「数学やプログラミングに自信がなくても大丈夫。
今のスキルにAIを“掛け合わせる”だけで、誰でも“経験者”になれます」「大切なのは、“やってみる勇気”と、“学び続ける姿勢”。
文系でも、未経験でも、何歳からでも遅くありません」──自信を持って、次の一歩を踏み出してみてください。
※出典:キカガク公式インタビュー
事例③|「AIを使う側になりたい」事務職からAI活用企画職へ
日々の業務をこなす中で、将来への漠然とした不安を抱えていた大西さん。
マーケティングの現場に身を置きながらも、「これからはAIを使いこなせる人材が必要になる」と直感的に感じていたそうです。
「AIは気になる。でも、自分にできるのか不安」
そんな葛藤を抱えながらも、大西さんは6カ月間の学びに飛び込みました。
結果、マーケティング×AIという“自分だけの武器”を手にし、仕事に対する視点も、行動も、大きく変わったのです。
「AIが使えるようになったら、何が変わるのか知りたかった」
大西さんのこれまでのキャリアは、主にマーケティング領域でした。
データ分析やお客様の声を集める業務には慣れていたものの、ツール任せの集計や手作業での処理に、限界を感じていたそうです。
「AIってよく聞くけど、自分の業務でどう使えばいいのかわからない。でも、“わからないまま”でいいのか──そんな気持ちが強くなっていったんです」
キカガクの受講を決めたのは、無料説明会で「初学者向けで分かりやすい」という評判や講座の設計方針を聞き、「これなら続けられそう」と直感したそうです。
学びながら見えてきた「自分の課題」と「作りたいもの」
受講当初は、正直なところ「自分に何が作れるか」すら見えていなかったといいます。
「何か作りたいという気持ちはあっても、明確なゴールはなかったんです。でも、学びが進む中で“これは業務に活かせるな”と思うことが増えていきました」
最終的に完成させたのは、製品の口コミデータを自動で集め、可視化するアプリケーションでした。
ネット上から自動で情報を取得するWebスクレイピングの技術や、Pythonによるデータ分析スキルを組み合わせて、「現場で使えるAI活用ツール」を自ら形にしました。
わからないからこそ「まず手を動かす」──そう決めた6カ月
大西さんにとっての最大の壁は、時間の確保と“理想とのギャップ”。
「はじめは“全部をちゃんと理解しなきゃ”と身構えてしまって。でも、途中から“まずは書いてみよう”って切り替えたんです」
わからなくても手を動かす。まずは真似する。エラーが出たら検索する。
こうした行動を積み重ねるうちに、気づけばプログラムを組み、課題を解決する力が育っていたといいます。
仲間との学び合いが、想像以上の効果を生んだ
また、学習中は同期との交流が大きな支えになったそうです。
「後半3カ月はアプリ制作期間だったんですが、同期の人とお互いの進捗や学びをシェアする中で、自分にない知識がどんどん入ってきました」
特に印象的だったのは、LINEのチャットボットやTwitter APIを活用したアプリ事例でした。
「自分の制作とは別でも、仕事に応用できそうなヒントがたくさんありました。学びって、“一人で完結しない”ほうが深まるんだなと思いましたね」
AIは“人のために使える”と確信した瞬間
受講後、大西さんはAI技術を使って、失読症の方向けの支援アプリ開発にも取り組み始めています。
「人の困りごとをAIで解決できるって、すごく素敵だなと思うようになったんです。自分が学んだことが、人の役に立つと実感できるようになった」
今では、同期メンバーと自主的に勉強会を継続中とのこと。スキルアップを止めることなく、新たな課題にも挑み続けています。
迷っているなら、まず“ひと通りやってみる”
最後に、大西さんはこんな言葉を残しています。
「これまで、独学でプログラミングや AI を学習してきて挫折をしてしまった方や、学習をしてみようとおもって躊躇をしている方にとてもおすすめなコースです!」
「機械学習だけではなく、スクレイピングやアプリケーションの作成まで欲張って学びたい方には、ぴったりはまるコースだと感じてます!」
今の仕事にAIを活かしたいけど、ひとりでは難しそう。そんな悩みを抱える人にとって、大西さんの挑戦と変化は、きっと未来を照らすヒントになるはずです。
※出典:キカガク公式インタビュー
コストパフォーマンスと給付金制度の仕組み
「受講料が高い…でも、それ以上の価値が本当にあるのか?」
「給付金が出るって聞いたけど、誰でも使えるの?」
そんな疑問を感じている方に向けて、この章では「実際にいくら負担することになるのか」「給付制度の仕組み」「手続きや条件」まで、やさしく丁寧に解説します。
給付金適用後の費用イメージ【70%/80%の違いも解説】
まず、キカガクの2大コースはともに厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」の対象講座です。
ただし、「最大70〜80%が給付される」という表現には注意が必要です。
給付率の違い(2024年10月以降)
| 給付率 | 適用条件 |
|---|---|
| 50% | 講座を修了した場合 |
| 70% | 修了後、1年以内に就業した場合 |
| 80% | 上記+「前職と比べて賃金5%以上アップ」が確認できた場合(※条件あり) |
※支給上限額:年間最大64万円(2024年10月以降)。
1年以内に複数講座を受講する場合は、合計額が上限を超えるとそれ以上は給付されません。
■AI・データサイエンス長期コース(長期)
- 受講料:792,000円(税込)
- 公的支援ありの場合の負担例:
| 給付率 | 給付額(上限あり) | 実質負担額 |
|---|---|---|
| 50% | 396,000円 | 396,000円 |
| 70% | 554,400円 | 237,600円 |
| 80% | 上限640,000円のため 実質支給 ≒ 560,000円前後 | 約232,000円 |
■生成AIビジネス実践コース(2カ月)
- 受講料:264,000円(税込)
| 給付率 | 給付額(目安) | 実質負担額 |
|---|---|---|
| 50% | 132,000円 | 132,000円 |
| 70% | 184,800円 | 79,200円 |
| 80% | 211,200円(最大) | 52,800円 |
※注意:給付率80%は「就業+賃金5%アップ」が必要です。
また、生成AIコースは地域のハローワークによって「給付対象外」と判断されるケースもあります。
補助金申請フローをわかりやすく解説
実際に給付を受けるには、あらかじめ以下のステップを踏む必要があります。
申請の全体フロー
- 受講開始日の1か月前〜前日までに、ハローワークで「事前申請」
キャリアコンサルティング(ジョブカード作成)が必要
被保険者期間が2年以上(初回受給) or 3年以上(2回目以降)が原則 - キカガク講座を受講(長期:6カ月/生成AI:2カ月)
- 修了後に必要書類を提出し「給付金申請」
就職証明書が必要な場合あり(70%・80%給付時) - ハローワークの審査
- 2〜3カ月後に銀行口座へ支給
ポイント:
・給付金は「後払い」。講座費用は事前に全額支払いが必要です
・支給は分割 or 一括:
└ 長期:50%(修了)+20 or 30%(就業)
└ 生成AI:原則1回支給(修了後)
受講料と還付のタイミング早見表
| コース | 支払い | 還付 | 支給時期 |
|---|---|---|---|
| 長期 | 全額前払い | 2回(修了後+就業後) | 修了後2〜3カ月+就業証明後 |
| 生成AI | 全額前払い | 1回(修了後) | 修了後2〜3カ月 |
自分が対象かどうか確認しよう:給付金対象者チェックリスト
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 雇用保険加入期間 | 初回:2年以上/2回目以降:3年以上 |
| 離職中 | 離職後1年以内に受講開始であれば可 |
| 年齢制限 | 原則なし(ただし別の補助金では〜45歳の制限あり) |
| 自主退職でも対象? | 問題なし(自己都合退職OK) |
| 賃金増の要件 | 80%給付を目指す場合のみ必要 |
口コミ・評判から読み解く実像
「キカガクって実際どうなの?」
「難しいという評判に誤解があることは分かったけど、本当に自分でも大丈夫かな?」
受講を検討している方の多くが、そんな不安や疑問を抱えています。
ここでは、Googleレビュー・SNS(X)・受講生インタビューなどをもとに、「キカガクの評判は本当のところどうなのか?」を冷静に読み解いていきます。
良い口コミ・悪い口コミをバランスよく紹介しながら、最終的に「自分に合うかどうか」の判断軸まで提示します。
良い口コミ:高評価が集まる3つの理由
キカガクには、特に以下の3点に関する好意的な評価が多く集まっています。
1. 教材がわかりやすく、ステップ設計が丁寧
「講義が一方的じゃなく、“なぜこの手法なのか”まで説明してくれるから、理解が深まる」(Googleレビュー)
「数学が苦手だったけど、図解+アニメーションのおかげで抵抗感がなくなった」(X投稿)
特に長期コースは、Python → 機械学習 → 深層学習 → ポートフォリオ制作という順序で構成されており、「自然に学びを積み上げられた」という声が多く見られました。
2. 転職支援の質が高い(doda提携)
「キカガクのカリキュラム内容を理解したうえで推薦文を書いてくれる。企業側への伝わり方がまるで違う」(インタビュー)
「他社スクールでは紹介止まりだったけど、キカガクは書類通過率も明らかに上がった実感がある」(X投稿)
未経験からAI・データ系職種へ転職を目指す人にとっては、心強いバックアップ体制と言えるでしょう。
3. 質問・学び合いの環境がある
「Slackで気軽に質問できて、24時間以内には返ってくる。サポートがあるから乗り切れた」(SNS)
「講師だけでなく、同期とのやり取りが励みになった。チーム学習が続けるモチベーションに」(Googleレビュー)
講師からの回答は平日10:00〜19:00・原則24h以内という目安があるものの、「質問が放置された」という口コミは見られませんでした。
悪い口コミ:決して楽ではないカリキュラム
ポジティブな声がある一方で、いくつか気になる口コミが見られます。
1. 学習時間の確保が思ったより大変
「平日は1日1時間、土日は3〜4時間やってギリギリ。スケジュール管理が肝だった」(X投稿)
「最初は余裕だと思ったが、課題や自走学習で意外と時間がかかった」(Googleレビュー)
特に長期コースでは、動画130時間+自習を含めると300時間以上の学習量が平均的な目安となります。
週10〜15時間程度を継続する必要があるため、社会人や子育て中の方にとってはある程度まとまった時間を確保することが求められます。
2. 初期の環境構築でつまずくことがある
「Jupyter Notebookの立ち上げで1週間迷子になった。もう少し初期支援があるとありがたい」(X投稿)
環境構築に難しさを感じる方もいるようですが、これはキカガク以外のスクールでも同じでしょう。
3. 内容が濃く、想像より大変だった
「最初は“動画見てるだけ”だと思っていたが、課題やアウトプットの量が多く、結構本気でやる必要あり」(X投稿)
「難しい問題も多く、結果的には自信につながったけど、甘く見ているとしんどいかも」(Googleレビュー)
想像以上に難しかったとの声が見られますが、そもそもAI自体が簡単な分野ではありません。だからこそ学ぶ価値があると言えるのではないでしょうか。
総括:受講を決める判断軸
キカガクの評判を見ると、このサービスは「真剣に学びたい人にとっては強力な味方」と言えるのではないでしょうか。
一方で、「気軽に試してみたい」「忙しくて継続できるか不安」という方にとっては、あらかじめ時間確保やマインドセットが求められる講座でもあります。
最終的には下記の2点をよく意識して受講を決めるべきかと思います。
- 自分の目的やライフスタイルに合っているか?
- 学びきる覚悟と準備ができているか?
✅ 最短の答えは「無料カウンセリング」で聞いてみること
口コミをいくら読んでも、自分に合うかどうかは実際に話してみるのが一番の近道です。
キカガクでは、無料で講師やスタッフと個別相談ができるオンライン説明会を実施しています。
お悩みの方はぜひ下記公式サイトから個別説明会にお申し込みください。
FAQ:よくある質問とその答え
Q1:どのコースを選ぶべきかわかりません
A:目的とゴールに応じて選びましょう。迷ったら無料の個別説明会で相談するのが確実です。
- 業務の効率化やAIリテラシーの向上を重視する方
→ 「生成AIビジネス実践コース」 - AIエンジニア/データ分析職への転職、副業収益化を本格的に目指す方
→ 「AI・データサイエンス長期コース」
副業目的で案件を獲得したい場合、実務スキルやポートフォリオ支援が整っている長期コースは現実的な選択肢です。
ただし、近年は生成AIを活用した副業(業務効率化提案や社内チャットボット開発など)も広がっており、生成AIビジネス実践コースを通じてそうした分野に挑戦する選択肢もあり得るかと思います。
「どちらのコースがより自分に合っているか」は、無料の個別説明会で相談してみてください。
Q2:給付金申請に必要な書類・タイミングは?
A:申請は「開講月の前月初〜開講日前日まで」に完了させる必要があります(地域によって締切が早まる場合もあります)。
申請準備は2か月前には開始するのが理想です。
必要書類の一例:
- 教育訓練給付金 支給要件回答書(本人記入+勤務先押印)
- 雇用保険被保険者証/在職証明書
- 本人確認書類(免許証など)
- キャリアコンサルティング修了証(ジョブ・カード発行)
※「教育訓練経費等確認書」はスクールが発行するもので、申請時点では不要です。
また、会社員の方は「教育訓練支援給付金(失業給付相当)」の対象外です。給付種別は雇用形態により異なるため注意が必要です。
Q3:E資格を目指すには何が必要ですか?
A:長期コース単体では受験資格を得られず、以下の条件すべてを満たす必要があります。
- 「E資格対策コース」(198,000円/給付対象外)を別途受講
- 事前確認テストで満点取得
- JDLA(日本ディープラーニング協会)に試験当日までに会員登録
キカガクのE資格講座のサポート体制を活用すれば、未経験からでも十分に合格が狙えます。
Q4:転職支援はどの業種・職種に強い?
A:キカガクはdodaと連携し、AI・IT・データ系職種に特化した支援を提供しています。
主な支援対象職種:
- AIエンジニア(画像認識、自然言語処理)
- データサイエンティスト/アナリスト
- データ活用型マーケター/業務改善PM など
職務経歴書の作成支援や企業推薦書の発行など、“AIを学んだスキルを転職書類にどう活かすか”まで伴走してくれる点が特徴です。
最後に|まずは個別説明会で相談するのがおすすめ
プログラミンを独学した場合、どれくらいの割合で挫折してしまうかをご存知でしょうか?
一説によると、90%を超えると言われています。
私自身、いくつかのプログラミング言語を独学しましたが、中には挫折してしまった言語や分野がありました。
原因は
- 作りたいものなど目標が明確でなかったこと
- 書籍やネットの情報だけでは本当に必要な知識を選別することが難しいこと
- プログラミング特有のフィーリングが一人では身につかないこと
にあります。
確かに生成AIの登場で学習は格段に効率化されましたが、こららのハードルを超えることは難しいでしょう。
私自身まだまだ勉強中の身ですが、これらの経験から学習において最も大切なものは環境であると確信しています。
この記事を読んでくださった方は、プログラミングや生成AIを学習中、あるいはこれから一歩を踏み出されることかと思います。
ぜひ、大切な時間を無駄にしないように、より優れた環境に飛び込んで学習をスタートしていただければ幸いです。
\ 30秒で簡単申し込み /
\ 30秒で簡単申し込み /